*本記事はプロモーションを含みます。
プチ移住前の問題|確定申告ができない
私と夫は、「働きながら旅をする」国際カップルです。今回は、プチ移住前に済ませてきた「準確定申告」についてお話しします。
2人とも個人事業主のため、毎年2月から3月には確定申告をしなくてはいけません。
しかし、このプチ移住を決行した年、私たちは12月に日本を出発することになっていたため、その時点でいつも通りの確定申告ができないということに気付きました。
そこで、他の選択肢を含めて私たちがどのように対処したのかをお話しします。
先に結論をいうと、私たちは出発前に「準確定申告」を行いました。詳しい内容、その他の選択肢については下記で紹介しています。
こういう特別なケースは、管轄の税務署の人に直接聞くのが一番だと思いますが、あくまでも一つの例として読み進めてください。
確定申告
毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得を翌年2月16日から3月15日までに申告する。所得税を納付する。
本来、その年の所得(例えば、2024年度、令和6年に稼いだ分)は、翌年(2025年、令和7年)の2月に申告しなければいけません。
今回の問題
上記の確定申告の期間に出国しているため、申告ができない。
では、続きをどうぞ。
確定申告期間に日本に在籍しない場合の対処法
通常通りの確定申告ができない場合、どう対処したらいいのでしょうか。
まずは、選択肢3つをお話しします。
親族に代わりに確定申告をしてもらう
書類の作成までは自分たちでやり、日本にいる家族に書類を税務署まで郵送してもらうという方法です。作成までは自分たちでやらなくてはいけなかったり、家族に年収がいくらなのかがバレてしまったりすることが難点ですが、税理士を雇わなくていい分安く済みます。
ちなみに、海外転出届を出した時点でマイナンバーカードを返却しなくてはいけません。e-taxはマイナンバーカードがないと使えないため、e-tax(オンライン)での提出ができません。そうなると郵送か直接税務署に持っていくかのどちらかになります。
私たちの場合:
このやり方の場合、書類作成は全て自分たちですることになります。今回は異例なケースだったため、確認できる相手が必要だと感じた私たちは、この選択肢は諦めました。
税理士さんに依頼する
書類作成から提出まで全て税理士さんにおまかせする方法です。プロにおまかせするという安心感はありますが、費用がかかってしまうのが難点です。
ちなみに「ミツモア」というサイトで税理士さんの一括見積もりを依頼してみたのですが、平均相場は7万〜10万ほどでした。無料相談に進めば、見積額から割引される場合もあるようです。
私たちの場合:
結局、無料相談には行きませんでした。なるべく費用を抑えたいと考えていたため、他の選択肢を探すことにしました。
★”準”確定申告をする
一般的には、年度の途中で亡くなった方の確定申告を行うときにするのが「準確定申告」というのですが、年度の途中で出国する人もこの「準確定申告」をすることが可能だそうです。ただし、申告する段階でその年の売り上げが確定していることが条件となります。
色々と悩んだ結果、出国前に確定申告ができるこの選択肢でいくことにしました。
準確定申告までの流れ
税務署に電話で確認
特殊なケースのため、まずは「準確定申告」が可能かどうか税務署に電話で確認を取りました。その連絡をしたのが10月頃(申告の2ヶ月前)です。かなり不安だったので、12月に相談予約も取りました。そこで書類作成、提出までサポートしてもらうことになりました。
この税務署の予約は、年末になると埋まっちゃうこともあるようなので、なるべく早く連絡したほうがいいかと思います。
書類作成の準備
私は、普段、マネーフォワードの会計ソフトを使っています。簿記の知識がほぼゼロな私でも簡単に会計処理ができるので助かっています。今回は、税務署でサポートを受けながら書類作成をすることになっていたため、毎月の売り上げや、費用がどこに書いてあるのかなど、パッと見て自分が理解できるように整理しておきました。提出する書類の作成は、この会計ソフトの内容を元に作るので、ミスや漏れがないようにしておきましょう。
無料の確定申告自動化ソフト マネーフォワード クラウド確定申告税務署で提出書類の作成、提出
税務署では、担当の方のサポートを受けながら、提出書類を作成しました。残念ながら、「準確定申告」は税務署のパソコンでは提出できず、また持参したパソコン(Mac)ではe-taxのソフトがダウンロードできなかったため、結局オンライン申請はできませんでした。ちなみにオンラインで提出すると10万円の控除を受けることができます。
私たちは、青色申告を行ったので、その提出書類と、税務署に持っていった書類等も書いておきます。
提出書類(青色申請)
・所得税青色申告決算書(一般用)(1枚目)損益計算書
・所得税青色申告決算書(一般用)(2枚目)損益計算書の内訳
・貸借対照表
持っていった物
・所得がわかる物(源泉徴収票など)、または所得を計算したもの(会計ソフト)
・社会保険、その他保険の控除証明書
・ふるさと納税の寄附金受領証明書
・マイナンバーカード
社会保険控除証明書やふるさと納税の寄附金受領証明書は、原本かコピーを提出するように求められました。原本を残しておきたい人はコピーをとっておくのがおすすめです。
ここまできての落とし穴|口座名義の確認を
書類作成が終わり、納付した所得税が還付されることになりました。しかし、ここで問題がありました。というのは、この還付を受けるためには、事業主本人名義の日本の口座を使用しなくてはいけません。
夫🇺🇸は、日本の口座を持っていなかったため、このままだとお金を受け取れないということになります。
この場合は、「所得税・消費税の納税管理人の選任・解任届出書」という書類を提出すれば、新しく納税管理人となった人名義の口座で還付金を受け取ることができるそうです。
ちなみに一緒に海外にいく私は、この納税管理人にはなれません。
ということで結局家族に納税管理人になってもらうことになりました。残念ながらその場では口座番号は聞けなかったので、家に持ち帰り、書類全部をまとめて郵送しました。
何はともあれ、なんとか「準確定申告」を終えることができました。
おわりに
いろいろとやり方はありますし、私の体験が参考になれば嬉しいですが、やはりこういうのはしっかり確認を取っておくことをおすすめします。正直、税務署に電話をする時は「こいつなんもわかってへんやん」みたいな態度で来られたらこわいなあと思っていましたが、実際かけてみると、親身に聞いてくださいました。職員の方にはもう本当にお世話になりました。
なので、ぜひ少しでも不安があれば聞いてみてください。
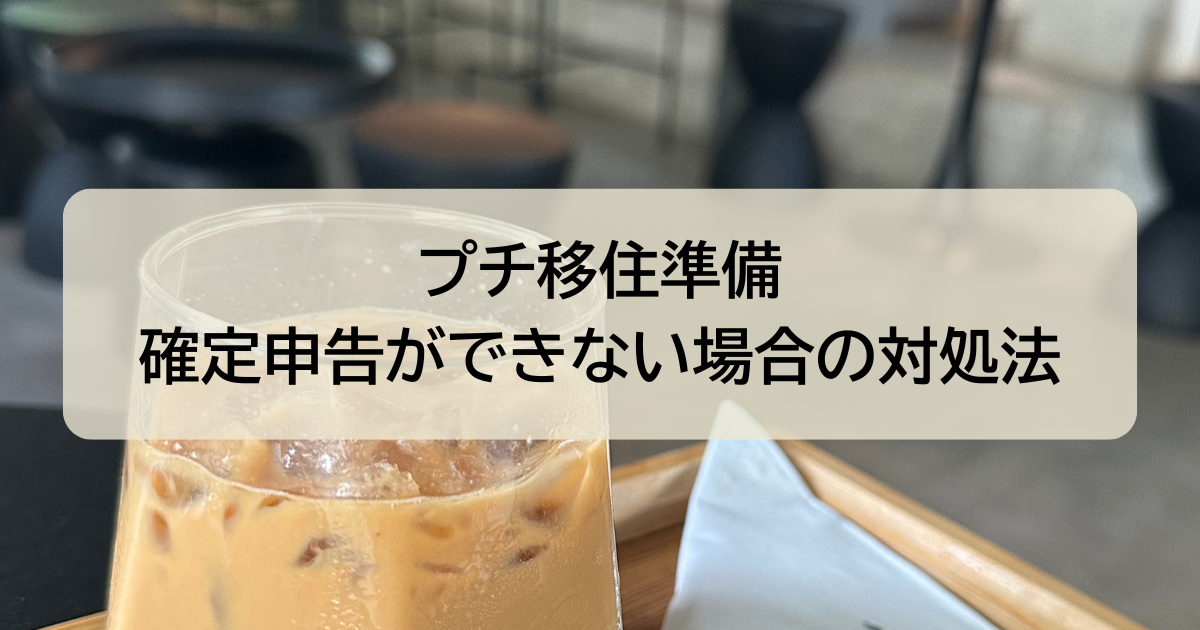
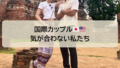
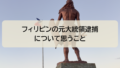
コメント